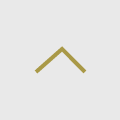激動の銀行時代から外食の経営者へ
ロイヤルホールディングス会長が語る経営者の役割
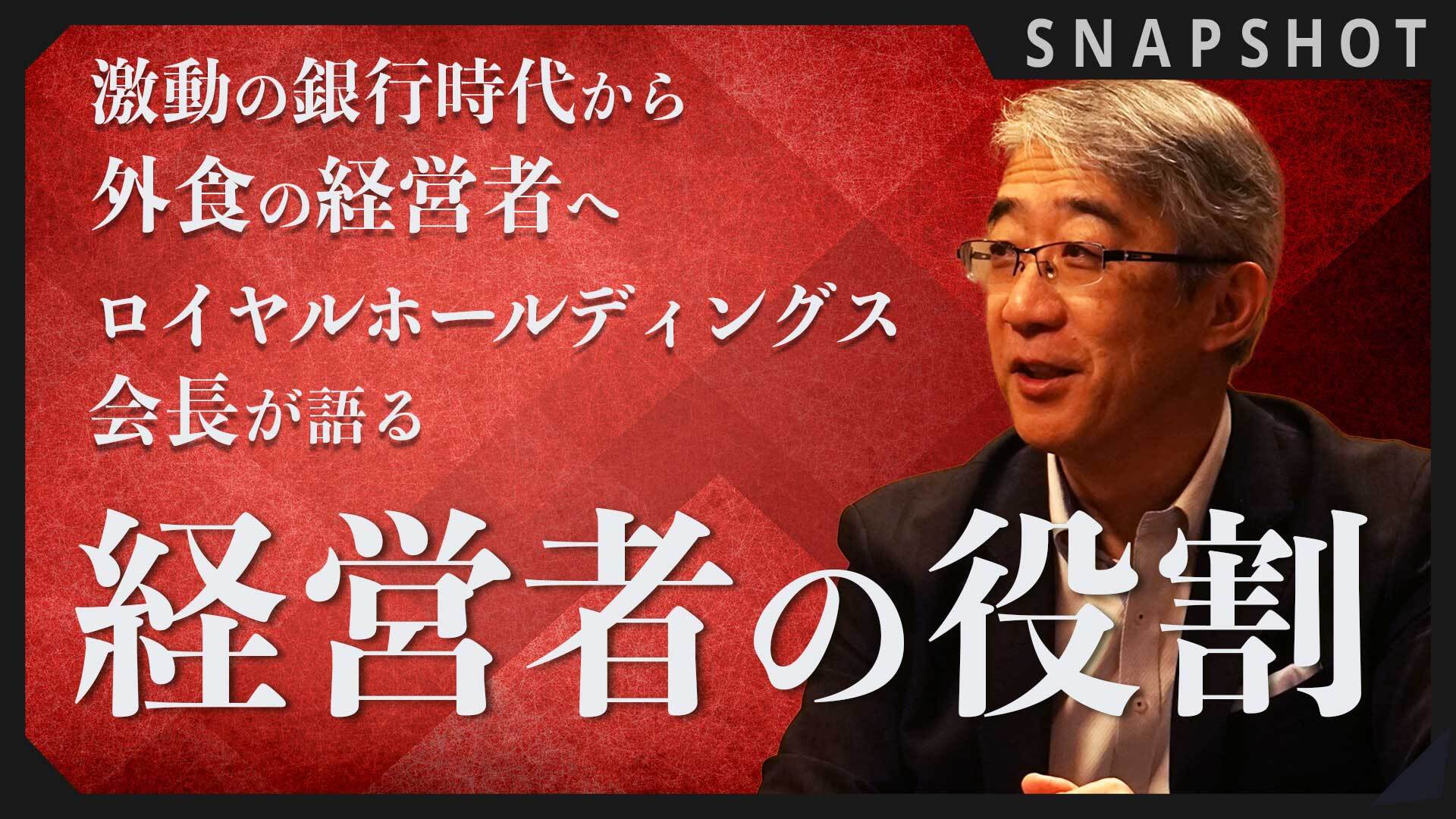
代表取締役会長
菊地 唯夫 氏
第二話では菊地氏のキャリアの変遷に迫っていこう。菊地氏のファーストキャリアは日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)。その後、外資系のドイツ証券を経てロイヤルに至っている。金融業界での経験は、その後の菊地氏のキャリアにどのように活きているのだろうか。
金融業界時代に目にした「危機におけるトップのあり方」
「金融業界での経験は、世の中の仕組みを理解する上でものすごく役に立ちます。株主の話や資本主義がどのように成立しているかも含め、学んだことを活かしたいと思って転職しましたが、結果、非常に役立ったという印象がありますね。なかでも、やはり東郷頭取から学んだことは今の私に非常に活きているでしょう」
東郷頭取は、90年代後半に金融危機が起きた際、最後に日債銀で頭取を務めた人物だ。不安定な状況に陥った会社を何とか立て直そうと取り組んでいたが、大きな流れに抗うことはできず、公的管理、実質破綻という結果を迎えた。東郷頭取は粉飾決算など証券取引法違反の疑いで逮捕され、13年間もの裁判の末、無罪となっている。当時30代に入ったばかりの菊地氏は、そんな東郷頭取の秘書を務め、会社の危機に立ち向かうトップの姿を見ていた。
「常に前向きな方でした。ふつうであれば、『自分は何も不良債権を作っていないのになんで俺が逮捕されるんだ、俺は救いに来ただけだ』と言いたくなるだろうと思うんです。なのに、東郷頭取は泣き言も愚痴も一切口にしなかった。危機のときの経営者はかくあるべきだと思いましたし、その後、コロナ禍の大変な時期には私の強い励みとなりました。
もう1つ印象に残っているのは、経営者と従業員との関係性に関する出来事です。日債銀を公的管理にするという命令が国から下された夜、東証で記者会見がありました。そのときの頭取の毅然とした姿が強く印象に残っているんですね。『我々は単独で生き残っていけるはずだ。しかし、国の命令が下ったため、取締役会でやむなく受託を決めた』という頭取のメッセージは、従業員に向けられたものだったと私は思っているんです。ぐっとくるものを感じました。この頭取は従業員に誇りを持っていたんだと」
被災地支援で実感した現場の強さ
日債銀が破綻したのち、ドイツ証券を経てロイヤルに転職したのは、「手触り感を求めていた」気持ちがあったという菊地氏。事業を実際に行うなかで、金融知識が役立つのではないかと考えての転身だった。その後、菊地氏は縁あってロイヤルへと身を移すことになる。当時の社長が菊地氏にかけた言葉は、「すごくいい会社だが、創業者の強い会社なため、ふつうの会社にしたい。それを手伝ってくれ」だったという。
「持株会社制にしていくであるとか、M&Aをするであるとか、そうした仕事は外資系でいくらでもやってきましたので、そうしたスキルを発揮するのが私の役割でした。
社長になってからは、スキルを活かすのではなく、会社を引っ張っていく役割を担うことになります。そのため、ここで大きな意識の転換があったと思うんですね。大きな転換期となったのは、社長になって1年ほど経ったころに起きた東日本大震災です。宮城県山元町に当社グループのメンバーで1週間炊き出しに行った際、コックさんたちがラインを作り、完璧なオペレーションで900人に温かい食事を提供している姿を見て、『すごいな』と思ったんです。さらには、宿泊所に戻ったあと、より満足していただくためにはどうしたらいいのか、延々とみんなで会議していた。この人たちは本当にすごいなと思いましたね。
そこで思ったのは、職場環境をきちんとすれば、この人たちはもっといい商品とサービスをお客様に提供できるはずだということ。平時でも被災地で見せたパフォーマンスができる会社はどうあるべきなのかという軸が、私の中に生まれたんです」
このときに菊地氏に生まれた軸は、日本のサービス業全般に通じる課題に繋がっている。その課題は「現場力依存症」だ。本来、現場力が発揮されるべきタイミングは一時的な急変時であり、平時に対応する状態を作るのは経営の仕事だと菊地氏は指摘する。構造的な変化に対しても現場力で何とかするよう求めてしまうと、現場の疲弊に繋がっていく。これが現場力依存症だ。
「こうした課題に気付けるのは、私が異業種の出身者だからかもしれません。同じ業界にずっといる人は、何でも当たり前になってしまい、違和感に気付きにくいでしょうから。例えば、外食産業でずっとやっている人は、単価も売り上げも来客数もすべてが上がることがベストだと捉えるでしょう。でも、私はそうは思わない。供給制約がなければ成り立つ話だとは思いますが、働き手が十分にいない状態で単価を上げると、お客様へのサービスが希薄化していくでしょう。来客数を上げるなら単価を下げる、単価を上げるなら来客数が下がらなければならないというのが、私の持論です」
与えられたミッションに精一杯尽くす。すべては「ゴーイング・コンサーン」のために
金融業界での経験が活きていることは多い。しかし、ピンポイントで「この経験がこれに活きた」といえるものはないと菊地氏は語る。大切なのは、銀行と証券、日本と外資という、まったく違う世界で経験を積んできたことだという。
「経営のアクションの最初のスタートは違和感だと思っています。ロイヤルで増収減益と減収増益が3年単位で繰り返されているという点に違和感を抱けたのは、金融業界での特定の経験があったからではなく、自ら望んだわけではなくとも複数の事業をいろいろな視点で経験してきていたからじゃないかと思うんです。
やはり大切なのは、多様な経験だと思います。1つの会社にずっといた人よりも、あれもこれも経験したというバラエティーさがある人。その引き出しの多さが話すなかで伝わってくるかどうか。幹部をヘッドハントする際には、そこに意識をしてもらえるといいのではないでしょうか」
とはいえ、異業種から飛び込んできた結果、失敗に終わるケースも珍しくはない。菊地氏は、なぜ成功への道を歩めたのだろうか。
「他の人との違いをあげるとするならば、『やりたいことがない』でしょうか。ドイツ証券に行ったのは銀行が破綻したからですし、ロイヤルに入ったのも社長になりたかったわけではありません。社長になったあとも『この会社をどうしたい』という思いを持っていたわけではありませんでした。夢がなさすぎると言われるかもしれませんが、私は自分の時間軸で物事を考えないようにしているんです。
私が重要視しているのはゴーイング・コンサーン。会社が続くことです。限りなく会社が繫栄していってほしいと考えたとき、私が『これを実現したい』と言うと、その瞬間に違う時間軸が入ってきてしまう。ですから、私の時間軸では物事を考えないのです。
それは無責任なのかというと、そうではありません。与えられたミッションに対しては精一杯務める。これは東郷頭取から学んだことですよね。あの人も、たぶん日債銀をこうしたいという思いはあまり持たず、再建したいという思いがあったくらいだと思うんですよ。どうしたいという思いよりも、与えられたミッションを精一杯がんばっていた。
私も同じです。ですから、社長は6年で退任するとはじめに決めていて、その6年で与えられたミッションに最善を尽くそうとしてきました。会長になったあとも同じで、何か実現したいという思いはないです。夢がないと言われてしまうかもしれないですけどね(笑)」
過去の経験から気付ける違和感を大切にしながら、ミッション完遂のために精一杯やるべきことをやる。すべてはゴーイング・コンサーンのために。日本の外食産業の未来についても考えるきっかけとなるひとときだった。