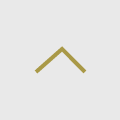ひらまつの社長が語る 価値を見出す劇場型経営

代表取締役社長兼CEO
遠藤 久 氏
記憶に残る料理を提供すること、目の前のお客様を幸せにすることだけを考えてやってきた
株式会社ひらまつは、全国で22のフランス料理、イタリア料理などの高級レストランのほか、7つのホテルを経営している。創業者が始めたひらまつ亭という一軒のレストランを皮切りに、レストランブライダルやオーベルジュ型のホテルなどに日本でいち早く取り組み、新しいカタチをつくり、成功させていった。
ラグジュアリーの代名詞となっているかのようなひらまつだが、それを率いる遠藤氏のキャリアのベースはマクドナルドだ。同じ飲食店であるものの全く異なる業態に位置するファーストフードで築いたキャリアをどのように活かしていったのか、はたまた転換したのか。その問いに対して遠藤氏はこう話す。
「なぜマクドナルドの遠藤が高級業態であるフランス料理やホテルの会社の経営をやっているのかという質問は何度も受けてきました。確かに単価が0二つ分違ったりするわけですが、僕の中では一貫性があります。それは、マクドナルドで28年間取り組んできたのはハンバーガーづくりのプロになることではなく、『VFM(バリュー・フォー・マネー)』の追求だからです。
マクドナルドの低価格かつ安定した品質、安全性などに加えて、フレンドリーなサービスが一貫して提供できる、そういう価値をどうやって最大化するのか。あとはそれを生み出せる人やチームをどうつくるかという話です。これは価格帯に関係なく、どんなビジネスでも通用する概念だと思います。
僕がひらまつでやってきたのは記憶に残る料理を提供することと目の前のお客様を幸せにすることですが、これも『VFM』の延長線上にあることです。」
遠藤氏の話は経営の基本概念としては理解できる。ただ、私自身ハンズオンで現場を支援してきた経験から、現場の実務がそう単純でないということもわかる。業態や単価が違えば必要なスキルや知識、もっと言えば提供する価値の種類が大きく異なる。そうでなくては高級業態など成り立たないだろう。
「そういう意味では、いわゆる作業的なものをアルバイトで仕組み化しているマクドナルドと、シェフ、サービス、ソムリエ、パティシエといったプロフェッショナルが価値提供するひらまつという違いはあります。そうすると、やはり彼らの人心をどう掌握してチームとして動けていけるのかという入り込み方は違いますよね。」
カリスマを失い、道を見失った中で見出した可能性
まさにその人心を掌握する方法が重要になるわけだが、どうやってチームをつくっていったのだろうか。ひらまつに参画する第一歩の取り組みとして、遠藤氏の人間性がまさに表現されたエピソードがある。社長就任前の段階で、役員や従業員が自分を受け入れてくれるのか、また自分が思い描く変革と彼らの認識にズレがないかを見極めるために、本音で話をする機会を持ったというのだ。
「料理人たちがマクドナルド出身の自分を受け入れてくれるのか、気になってはいました。だから、特に料理人のトップの取締役とはかなり膝を詰めて話をしました。
今までの延長線上にはない価値を追求していこうという話をしました。人材を育成して料理を研究する時間をもったり、コースの価値をさらに上げるためのペアリングやデザートを考えたり、サービスマンが正しく料理の価値を理解しお客様に伝えられるようになったり、というように、ただ料理が素晴らしいだけではなくトータルの価値をチームとして向上させていけるかがとても重要になってくると伝えたんです。
その上で、自分が考えるやり方はこうで、ひらまつでそれが必要とされているなら一緒に改革できると思うけど、そうじゃないなら僕が来ても難しいだろう。シェフどう思いますかという本気の対話をしました。」
数時間かけて話した後、そのトップシェフはまさに遠藤氏が指摘した内容がこの会社に欠けていることだと本音を話してくれたという。そして、新しいひらまつを創生していくためにぜひ一緒に働いてほしいと話してくれた。
ところで、遠藤氏がひらまつの経営の手綱を握ったのは2020年、コロナで赤字に転落したタイミングでカリスマ創業者からのバトンを受ける形だった。ビジネスパーソンとしても料理人としても突き抜けた存在だった創業者は40年間に渡り国内随一の高級業態をけん引してきた。そのような創業者の持つカリスマ性を失ったなかでの交代劇だったのである。
「事業30年説と言われるように30年経ってくるとやっぱり限界が来るわけです。ひらまつの場合40年です。カリスマがいたからこそここまで大きくできたけれど、ある時ふと後ろを振り返った時に後継者がいなくて、これからどこへ向かうべきなのかを見失ったわけです。でも今まで培ってきた知見、料理、サービスという経験値や価値はいっぱいあるわけだから、その価値を使って次に繋げることを模索していけばいい。そうやって一緒に将来を作っていくことに彼らも僕も可能性を見出したんです。」
コロナ禍で磨き上げた新しい価値
社長就任前からキーパーソンと踏み込んだ議論をしてきた遠藤氏だが、実際にひらまつに参画してからは目指す姿をどう実現していったのだろうか。まさにコロナが猛威を奮おうとしていた2020年、株主総会が行われる6月に先駆けて3月に顧問として着任したが、その2日目に緊急事態宣言が発出されたのである。
「そこからますます業績が悪化しました。これ以上ないぐらいまさに火中の栗を拾うような状態で、よく飛び込んで行きましたねって言われるんですが僕にはそう見えていなかったんです。ひらまつは必ず伸びると思っていました。
ポイントは3つあって、1つ目は、ひらまつはいい価値をたくさん持っているのですが、後継が育ってなかったりチームができていなかったことによって磨き込まれていませんでした。2つ目は伝えきれてない価値があるということでした。3つ目は、ひらまつは日本でほぼ初めてに近いくらいフランス料理というものを星付きで立ち上げたり、レストランブライダル、オーベルジュなど常に時代の先端を作ってきた存在だったのに今は攻める姿勢を失っているということ。今まで作ってきた価値をもう一度磨き上げて、お客様にしっかり伝えて、もう一度時代の先を作っていくような価値作りをしていけば必ず復活できます。」
遠藤氏によるとレストラン、ブライダル、ホテルという三事業を一気通貫で持っている企業は日本国内にも世界にも存在しないという。つまり、唯一無二の価値が提供できるのは必須であり、リスクよりも可能性やポテンシャルの方が大きいと確信していたのだ。
ところで、遠藤氏の話の中に頻繁に登場するキーワードとして「LTV(ライフタイムバリュー)」という言葉がある。ひらまつのLTVとは何か。
「ひらまつが提供できる価値は人生すべてに寄り添っていけるんです。まず『食』は、全ての人に提供できる機会があります。単に美味しいものを出すだけではなくて、料理を囲んで大切な人と記念や思い出になるような時間を提供します。
また、ハレの日のピークを彩るのがレストランブライダルですが、ここを遡れば、プロポーズ、初デート、初フレンチなんていう形で人生の節目に接点があります。
さらに結婚式が終わった後のアニバーサリー、お子様が産まれたら出生祝い、お食い初め、お誕生日、というように関わっていけます。ずっと先に行くと、今度は三世代で旅行に出て、美味しいものを囲みながら宿泊するというオーベルジュ事業。このように単なる食事から人生のハレの日全てを盛り上げていけるわけです。」
ハレの日を人生に沿った線でつなげて最大限にご支援していくのがひらまつのLTV事業なのだろう。さらに遠藤氏はひとつの取り組みを紹介してくれた。
「エルヴァージュボックスという企画を始めました。これはワインを入れる桐の箱なんですが、結婚式に参加された方たちに1年後のご夫婦に対してメッセージを入れていただくんです。鍵を閉めて1年間保管します。そして1年後、挙式の日と同じ料理を二人で召し上がっていただく間にメッセージ付きのワインが運ばれてきて、いわゆる二次会が1年後に行なわれるというわけです。」
劇場型経営が導き出す成果
このエルヴァージュボックスのアイデアはLTVの価値づくりのディスカッションをする中で若手の社員から出てきたものだという。遠藤氏はいわゆる「プロ経営者」のイメージにありがちな、トップダウンでドラスティックに現場を変えていくのではなく、ボトムアップの意見を反映していくきめ細かい経営手腕があるようだ。
「僕がやっているのは劇場型経営といって、そこで働く人たちが自ら価値を磨き上げ、伝達し、新たな価値提供を行っていくことです。社長が全ての答えを持って指示するんじゃ今の時代は対応できません。これからの時代の経営というのは働く人たちが主体性を持って具体的な行動を起こしてワンチームとして価値を生み出さなきゃいけない。これをどのように引き出すのかを大切にしているんです。」
ここで看板商品の「黒トリュフのスープ」が運ばれてきた。遠藤氏は楽しそうにこのスープが「看板」となった経緯について解説してくれた。
「僕が着任して最初にやったのはオペレーションセッションといって、コックコートを着て現場に出て、ポールボキューズっていうブランドの価値はどんなもので、どこへ向かっていくべきなのかを議論することでした。そして、ブランドを象徴する商品を明確に作ろうと言ったんです。そこでブランドの成り立ちや軌跡を振り返って議論して、皆が自信をもってお勧めできる商品として出てきたのがこのスープだったんです。
だったら全員でもう一回このスープの本物の味を学び、知り、みんなで伝え、売りに行こうよということになって、そこから一気にこのスープが売り出されて、高単価にも関わらず過去にないぐらい売れ、季節商品にも展開されるようになって非常に成功しました。」
ファンドとの協創
遠藤氏の手腕が如何なく発揮され、チームワークの醸成を生み成果につながった典型的なエピソードだ。ところで遠藤氏はファンドの推薦で参画した経緯があるが、ファンドとの関係性をどのように構築しているのだろうか。
「ファンドと一緒にやっていくには共通言語を持つ必要があって、方向性や考え方を当初にかなり詰めておかないといけません。それでも少しずつ合意の差異が生まれてくるので、常に合意形成しながら進めていくことがとても重要です。
あとは経営合宿みたいなのを最初に必ずやるんですね。そこで徹底的にファンドが持っている言語と現場が持っている言語、今からやらんとしていることの意味合いをすり合わせます。これはつまり、経営の言っている『何で現場はできないんだ』と現場が言っている『経営は一体何を考えてるんだ』の間のギャップを取り除くことです。
ファンドと現場で起こる2つの議論、つまり『あるべきto be』と、『現場の課題』の議論をいっぺんにするとかみ合わないんです。なのでそれを整理してどのようにすればあるべき姿に到達できるのかというアプローチの議論を合宿でやるんですね。
それで、行動の話になったらトップダウンでやるべきところもあるんですけど、原則は自らが主体的に行動できるようにしていくために僕が来ましたという理由をしっかり伝えます。」
あるべき論を語りがちなファンドと目の前の課題に終始しがちな現場のノウイング・ドゥーイングギャップを初期段階で一気に埋め、準備を万全にしてスタートダッシュを切るということだ。ファンドとも現場とも共通言語を持ち、自らがハブとなってコミュニケーションギャップを埋めに行く。そうして文字通り巨大なワンチームを組成し、『記憶に残る料理の提供』と『目の前の人を幸せにする』という目標を成し遂げてきたのだ。