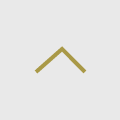ロイヤルホールディングスの苦境を打破した ポートフォリオ経営

代表取締役会長
菊地 唯夫 氏
外食産業のピークを境に、3年周期で経営状態が変化。リーマンショックでは2年連続赤字に
ロイヤルホールディングス株式会社と聞くと、印象が強いのはロイヤルホストだろう。ただ、実際にはいろいろな事業を展開しており、現在の主力事業は外食、コントラクト、ホテル、食品だ。
外食事業では、ロイヤルホストの他、「天丼てんや」や「シズラー」を展開。ホテル事業ではリッチモンドホテルを、食品事業は外食インフラ機能(製造購買・物流の運用)や冷凍食品「ロイヤルデリ」などを展開している。コントラクトは、社員食堂や高速道路のサービスエリア、空港内など、さまざまな施設にある「食」事業を指しており、各所にレストランや売店などを展開している。
ロイヤルの創業者は、当時、日本で水商売といわれていた飲食業を産業化するために人生をかけてきた立役者だ。ロイヤルは外食産業の勃興と共に歩んできた会社といっても過言ではない。
菊地氏がロイヤルに執行役員総合企画部長兼法務室長として入社したのは2004年。その後、2010年に代表取締役社長に就任。社長就任の直前となる2008、9年にはリーマンショックがあり、ロイヤルも2期連続赤字という非常に苦しい状況でのバトンタッチだった。菊地氏は、当時の自身の役目についてこう話す。
「とにかく黒字化させることが優先事項でした。ただ、もう少し過去を遡って業績を見てみたところ、1997年を境に、増収減益と減収増益を3年周期で繰り返していたことがわかったんです」
健全な会社は、増収増益を持続している会社だ。なぜロイヤルではこんなことが起きていたのか。
「よくよく考えてみると、裏にあったメカニズムはそう難しいものではありませんでした。97年は外食産業のピークで、そこから右肩下がりになっていっていたんですね。その状態で、当社グループでも10数年間、既存店が前年割れを続けていたことがわかりました。
既存店が前年割れしているのに売上が上がっていくということは、既存店のマイナス以上に新店を出しているだけ。既存店の売上が下がるということは利益率が下がるということで、新店もすぐには利益貢献しないことを考えると、簡単に増収減益になるんです。それを数年続けると、利益がだんだん0に近づいていく。
それでは何をするかというと、大体リストラだと。要は、不採算店を閉めて減損処理をして、新店は赤字になるからと凍結する。そうなると当然利益が上がります。そうすると今度は、売上が落ち込んで既存店はマイナスだから、また新店を出す。その繰り返しが、3年周期の増収減益、減収増益だったんです。実はそれは会社が徐々に衰退していくプロセスであり緩やかな変化が起きていた。もっと長い時間軸で大きなトレンドがどう推移しているのか、構造的な変化を見極めることが重要です」
「ゴーイング・コンサーン」を重視し、既存店の立て直しに注力
菊地氏の判断は、新規出店をやめ、既存店に集中するということだった。その判断を下したのは、菊地氏が大事にしている「ゴーイング・コンサーン」という考えにある。ゴーイング・コンサーンとは持続していくことを指す。企業は単に増益企業として生きながらえていくのではなく、常に継続していくことを前提としているということが菊地氏の考えだ。「増収減益・減収増益はゴーイング・コンサーンなのか」と考えた結果、その答えは否だった。
「市場が縮小していくことについては、我々の努力ではどうにもできません。でも、既存店がマイナスになり続けることは我々の努力で何とか変えられるのではないかと思ったんです。そのためにも、まずはとにかく既存店の復活。今お越しいただいているお客様の満足度を上げられるよう、改装や改修に全資源を集中することにしました。そこから、増収増益が6年以上続くことになったんです。
経営層と現場が乖離。従業員向け決算説明会や経営塾により、目指す方向性を揃えた
先述したように、菊地氏がロイヤルに入社したのは、総合企画部長兼法務室長としてだった。入社翌年、創業者が逝去。そこから、それまでのカリスマ創業者の元で事業運営をする会社から、みんなが市場に近いところで意思決定できる会社への変革を目指すことになる。
「当時のロイヤルは17社の子会社をつくり中小企業が集まったような状態。M&Aをしてもグループのシナジーがまったく利かない状態で、せっかくのグループの力が活かせていなかったのです。これが2008~2009年の2年連続赤字にもつながっている1つの要因で、そこからどう立て直していくのかがポイントでした」
3年周期でスパンが変わっている状態では、中期経営計画はあまり功を奏さないという。増収減益が3年間続いたあとのタイミングでは利益偏重になり、どうしてもこのサイクルを助長してしまう結果になる。その時間軸に惑わされずに長い時間軸で考えられるよう、菊地氏は10年の経営ビジョンの策定に着手。そのビジョンを達成するための最初の3年間として中期経営計画をつくるプロセスを踏んだ。
中期経営計画では、さまざまな事業ごとに役割を決めたという。ロイヤルホストはブランドの源泉と位置付けることで、既存店への再投資に注力。一方、ホテル事業やコントラクト事業はもっと成長させていく方針でいくといったフォローアップを採った。大きく変えることで、社内からの反発はなかったのだろうか。
「そもそも、私が社長に就任したタイミングは2期連続赤字で、実は内紛のようなことが起きてしまっていました。当時はメディアでも『老舗ファミレス内紛』といったことが取り上げられています。逆にいうと、そこが1つの踊り場になったのかなと。このタイミングで社長に就任した私に求心力があったかというと、そのようなことは決してなかったと思います」
当時の菊地氏が強く思ったのは、グループとしてどういう世界を目指していくのかをもっと従業員にきちんと伝えるべきだということだった。内紛が起きた背景には、経営層に対する従業員の不信感があったのだろうという。その不信感を払拭するには、経営層が今、何を考えていて今後どのように会社を経営していこうと思っているのかを説明する必要があると考えたのだ。
そこで、菊地氏が行ったのは半期ごとに行う従業員向けの決算説明会。そして、従業員の質問に答えるために始めた経営塾だ。
「決算が発表されると、投資家向けに説明会がありますよね。それと同時に全国を回って、従業員に会社の状況や目指している姿を伝えていきました。最初は東京、福岡だけで始めたのですが、『すごくおもしろいから、現場の人たちにも聞かせたい』という声が上がってきたため、回る場所を増やしていきました。
そこで必ずやっていたのが、従業員アンケートです。そこにある質問にメールで返しきれなくなったため、始めたのが経営塾です。朝7時半から9時までの計6回で、投資家にとってはシンプルでも、現場の人にとってはわかりづらい『なぜ今ROAを上げることが大事で、ROEを上げるのか』など、戦略の説明を始めました。受講者はのべ900人ぐらいになりました。
これを繰り返すうちに、現場と経営との間に立ちはだかっていた高い壁が、少しずつ下がっていった印象です。他には、1人で大体年間200店舗の現場を見に回ることも大事にしていました。事前に連絡すると準備を整えられてしまうので、リアルな瞬間を見るためにも、なるべく1人で行くようにしています。
会長になってからは、現場のヘルプに入ったりもしています。昨年のゴールデンウィークは羽田のロイヤルホストで皿洗いを担当しました。過去最高の売上の日で、社会人になって1番働きましたね(笑)。
取締役会は最近、社外役員が中心になってきています。それ自体は悪いことではないのですが、そうなると事業のことを知らない人が多くなってしまうんですね。でも、彼らは世の中の流れやプロフェッショナリズムは持っている。そうなると、事業との間に空白が起きてしまうんです。そこで、社長にはあえて事業の近くにいってもらい、私はちょうど中間に自分をポジショニングしています」
コロナ禍で気付いた、これまでのポートフォリオの脆弱性
最初の10年計画を終えたころにやってきたのがコロナ禍だ。外食産業全体がダメージを受け、ロイヤルも2期連続赤字となった。さまざまな事業があるにも関わらず、そのすべてがコロナ禍により大打撃を受けてしまったという。
「この産業にはいろいろな波があります。外食であれば低価格ブームや高価格ブームがあり、前者の場合はてんやが好調になり、後者の場合はロイヤルホストやシズラーが好調になります。コントラクト事業でも、円安が進むとインバウンド需要が増して空港施設の調子が良くなる一方、ガソリン代が上がるため高速サービスエリア事業の調子が悪化する。
このように、さまざまな外部環境に対して、ポートフォリオを持つことでリスクを最小化していこうというのがロイヤルの考え方だったのですが、コロナ禍では、たった1年で1,400億円以上の売上が約800億円まで落ち込んでしまいました。これは、リスク分散をしていたようで、本源的なリスクが一緒だったという表れです。要は、人流に依存しているグループだったと。そこで、取り組んだ一例ですが食品事業を強化して、人流に依存しないビジネスを育てていこうとしています」
食品事業の主力は冷凍食品だ。これは自宅に届けられるため、人流に依存しない。事業を再整理し、コロナ禍での経験を踏まえて、より強いポートフォリオの構築を目指している。
「食はなくなりません。外食産業はコロナ禍で大ダメージを受けましたが、食べなくなったわけではなく、中食や内食のニーズが増した。今後も『食』に向き合っていくことに変わりはありません。クオリティの高い食にこだわることは変わらず、そのフィールドが少し変わっていくイメージですね」
ポートフォリオを組むことは、これまでの菊地氏の話からもわかるように、会社のリスク分散になる。しかし、資源を分散せざるを得ないため、成長に関してはデメリットがあるともいえる。それでも、菊地氏はポートフォリオ経営を続ける道を選んでいる。その理由について、菊地氏はこう語る。
「我々が1つの事業しかやっていないと、打ち手がリストラしかなくなってしまうでしょう。でも、ポートフォリオを組んでいれば、他の調子のよい事業に人をシフトできる。昨今、株主資本主義からマルチステークホルダーにキーワードが移ってきています。我々のビジネスは人が直接的に価値を生むため、従業員が会社に向き合い、成長してくれることで会社がメリットを得られるんですよ。ですから、人の流動化がグループ内でできていること、グループ間でシナジーが生まれていることが重要だと思っています。
外食産業は、よくフードとレイバー、FLコストといいまして、コスト意識が強いんです。その視点をもう少しステークホルダー視点で考えるべきではないか。これが私が社長になってからずっと考えているポイントですね。だからこそ説明会もやるし、経営塾もやっているわけです」
将来を見据えたポートフォリオ構築が重要
菊地氏は、社長就任時にあった事業の位置づけを考え、再編することで事業ポートフォリオを組んだ。では、まだ単一業態しかない企業がポートフォリオを組むためには、何をしたらいいのだろうか。
「まずは、人口が減っていく日本社会において、本当に成長できる事業なのか、新しく成長でき、収益をもたらせる方法を開発することはできるのかを考えるといいでしょう。そうした打ち手がないのであれば、今の事業の強みを活かして、少し違った属性の事業に飛び地を作れないか検討する。これが大事なポイントだと思います。
ロイヤルも行っているのがM&Aです。M&Aはわかりやすい方法ではありますが、ある程度の資本があることが大前提であり、その資本で時間を買うものです。それだけの資本があるのであれば、M&Aを積極的にしていくのもありでしょう。
我々は2000年代にM&Aを積極的に行いましたが、当時M&Aを行っていなければ売上高600億、利益が9億円ほどの会社になっていただろうというのが2013年時点の試算です。M&Aは非常に有効な手段だといえるでしょう。
財務的に余裕がなく、M&Aのノウハウもない場合は、これからの将来を考えて新事業を作っていくほうがいいと思いますね」
資本さえクリアできれば、M&Aは会社をスピーディーに拡大できる有効な手立てだ。しかし、そこには注意点があるという。
「買収した企業を全て同じ色に染めようとしてはなりません。ロイヤルでは、てんやを買収したあとに、てんやの創業者から『このままだとてんやはダメになります』と言われたことがあります。それは、てんやを何でもロイヤルホストと同じようにしようとしていたから。例えばロイヤルホストは店長がスーツで店にくるのですが、当時てんやではジーパンでもOK。異なる文化を持つ会社に別の文化を押し付けると衝突を生むので、その会社の文化を尊重していくことが大事です。
そうしたさまざまな文化を持つ会社の人々が流動性を持って働けるようにするためにも、従業員向けの決算説明会が有効でした。懇親会でロイヤルホストやリッチモンド、てんやの店長や支配人が一堂に会し、グループのことを知ってもらった上で、事業は異なれど目指していることは同じだという共通認識を持ってもらう。その共感がスタートです。なお、大事なのはこの共感であり、スーツやジーパンは本質ではありません。創業からの空気を互いに理解できていることが大事です。
なお、ロイヤルは、菊地氏という人材を外から入れたことで今がある。これもヘッドハントするだけの資本が必要ではあるが、外部人材を入れることについて、菊地氏はどう考えるのだろうか。
「どうでしょう、私の場合は偶然ですからね(笑)。でも、外部の人材を有効活用するのは非常に重要だと思います」
ホスピタリティとDXの両立は10年計画でも一大テーマ
2010年に初の10年計画を立て、10年後が2020年と、コロナ禍に直面した年となった。くしくも、初めて10年計画を立て、そのビジョン達成に向けて中期経営計画を立てたときと似た環境になったわけだ。しかし、今度は即座に10年計画を立てることはしなかった。従業員から上がった「なぜ今回は作らないのか」という疑問に対して、菊地氏はこう説明する。
「以前は緩やかな低下に対して、緩やかな回復を目指しました。対して、コロナ禍による影響は急激な低下だったため、まずはV字回復を目指さなければなりません。10年計画を立てるのはもう少し後にしますと説明しました。今がちょうど新たな10年計画を立てているところです。前回はどちらかというとトップダウンで作成したのですが、今回はボトムアップで作ろうということで、従業員を巻き込みながら議論を進めているところです」
昨年からは、新たな10年計画を立てるためにRセッションを始めました。会社横断で各会場の参加者にロイヤルグループの10年後についてディスカッションしてもらい、ディスカッションチーム毎に発表をしてもらいます。またその発表を基に、私がファシリテーターとなって社長や執行役員とパネルディスカッションをするというもの。これは、10年計画を作らずに中期経営計画を作った際、『なぜ10年計画を作らないのか』といった従業員からの質問が届いた際に勉強会をやってみたことが発端です。そこですごく面白い議論ができたので、Rセッションという形を採ってみることにしました。綿密に考えるよりも、現場のちょっとした声を受けてやってみるのが大事だと思いますね」
次の10年計画でも、食のクオリティとホスピタリティを大事にするという基軸は変わらないという。加えて、ここ数年で発達を遂げているAIやテクノロジーを活用し、いかにアップデートしていくのかが重要な視点になってくると語る。
「この産業におけるDXは絶対に必要です。いろいろな業務があるなかで、人がやることによって本当に価値を生み出せること以外の部分をどんどんデジタル化して、人を価値創造に集中できる状況をつくる。テクノロジーと人の共存の道を探ることが大切です。
ロイヤルでは、2017年にデジタルは不可避だということで研究開発店舗を作りました。そのときに生産性を高めたのはキャッシュレスでした。でも、ロイヤルホストで完全キャッシュレスにしてしまうと、お客様がいなくなってしまう。
そこで現場が考えたのが、従業員が一切お金を触らなくて済む仕組みでのキャッシュレスでした。毎日のレジ締めの作業や、翌日の釣銭用意がレジ内で行われるようにする。お客様にお支払いしていただくときにも、機械相手だと無機質になってしまうため、対面レジを90度にすることで、お客様に寄り添える形にしました。これはすべて現場のアイディアなんです。
上が決めるのではなく、現場の人たちが使いやすいよう、意見を採り入れていくのが共存するテクノロジーを導入する上で必要不可欠な視点だと思います」
テクノロジーを取り入れるには、一定のコストが発生する。しかし、導入することで従業員に余裕ができ、それがより良いサービスにつながって付加価値が生まれるという視点があると菊地氏は語る。
規模の戦略的圧縮により休みも売上も増やす
テクノロジーから話は逸れるが、従業員の余裕がサービス向上につながり、売上増につながったエピソードとして、こんな話を披露してくれた。
「ロイヤルホストは、2011年から段階的に営業時間を大幅に短縮しました。早朝と深夜の売上は別事業でカバーできると踏んでゴーサインを出したのですが、結果として売上が上がりました。営業時間が減った分、お客様の多い時間帯にスタッフを適切に配置でき、よりサービスが向上したのが要因です。
また、2018年には正月を含め3日間を店休日としました。これも、年間で見ると売上増という結果が出ています。正月休みを取れた充実感、リフレッシュ感から、従業員が生き生きと働け、サービスの質が上がったことが要因でしょう。
昨年9月からは隔月で店休日を取り始めました。こうしたことを規模の戦略的圧縮と呼んでいます。縦軸が1単位当たりの創出価値、横軸が店舗数、営業日数、営業時間などの規模、その面積が企業の生み出す価値の総和だとして、労働供給の制約がなく人が補充できる状態であれば規模を拡大すれば価値が伸び続けますが、人を増やせないとサービスの劣化などに繋がるのです。そこで、規模を圧縮することで価値を上げる。これが規模の戦略的圧縮です。
隔月の店休日が上手くいけば、毎月にするかもしれません。そうすると、業界が変わるでしょう。私たちはそこを目指していかなければならないと思っています。そこに、どう上手くテクノロジーを組み込んでいくかということだと思いますね。
ただ、これはすべてにおいて該当するわけではありません。例として、てんやはファストフードなので、規模を増やしていく成長が可能です。どの外食産業もサイエンスとアートの組み合わせだと思っていまして、ロイヤルホストはアート8サイエンス2といった具合に、個々で異なるのだと思います。そしてその割合の答えは、やっぱり現場にあるのだろうと思っています」
日本の外食産業は最強。食とホスピタリティは日本の未来を作る基軸になる
日本において、食の豊かさは1つの大きな強みだ。その理由は、外食産業の多様性にある。さらに、そこに加わる「おもてなし」の要素が、日本の外食産業の価値の高さに繋がっている。
「その価値をもっと発揮できるよう、テクノロジーを活用していくことが重要だと思います。だんだんとコモディティ化していくなかで、私は食とホスピタリティは日本の未来をつくる上で絶対に基軸となると考えています。そのために重要なのが、まず誇りを持つことです。
私は今、京都大学の経営管理大学院で客員教授を務めているのですが、前の総長の山極さんがおっしゃっていたのが、『人間には五感がある』という話です。そのうち、嗅覚と触覚と味覚は共感ができない。でも、人間が信頼関係をつくるには、この共感できない五感が重要なのだそうです。要は、オンラインだけでは信頼関係はつくれないということでしょう。この嗅覚、触覚、味覚はまさに外食産業で同じ体験ができます。そうした体験を作り出す場を提供している産業として、外食産業は今後ますます日本にとって重要な産業になると思っています」