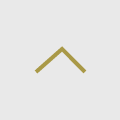#1 トライアルHD社長が語る 黒字を実現する可視化力

代表取締役社長
亀田 晃一 氏
無借金経営を続けてこられた秘訣
高橋:これまでほぼ無借金経営で売り上げも7000億まで伸ばして、店舗数も300店舗に迫る勢いということですが成長の秘訣はどの辺にあったんでしょうか。
亀田:元々金融機関で小売業を担当していたんですが、その中でキャッシュフローが持たなくなって成長が行き詰まるタイミングがあると思っていたんです。小売業を経営する中で1番重要なのはROIだと思っていて、投資効率さえ良ければキャッシュフローは回っていくんです。なので、キャッシュフローと投資回収がうまくまわるビジネスモデルかどうか、そこに注意しました。
僕は売り上げ1500億ぐらいの時にトライアルにジョインしたんですけど、当時は居抜きの出店方法を取ってたんですね。小売業っていうのは、お客様は現金で支払ってくれて、支払いの方は2カ月先の支払いだとかっていうサイトを取れるわけですよね。そうすると在庫の回転率さえ高ければ、資金がなくても成長できるんです。キャピタルがいらないので、高いROIを必然的に実現できるビジネスモデルがあった。だから途中から少しモデルを変えて新規出店をやってもここまで実質無借金で成長できたんです。
高橋:なるほど。順調に成長しているように見えますが、途中でつまずいたとかターニングポイントっていうのはありましたか。
亀田: 2000~2002年ぐらい、金融が非常に厳しくなって小売業が破綻したタイミングがあって、九州でも大手3社が破綻して空き店舗ができた。でもそれは2010年ぐらいまでの一時的な話で、居抜き出店できそうないい空き物件が出てこなくなったわけです。その先の成長を考えたら新規出店をしていくしかない。そこのモデル展開が1つの大きなターニングポイントだったと思ってます。
なんでも可視化するのがトライアル流
高橋:そうするとビジネスモデル自体を結構見直されたってことですか。
亀田:見直したっていうよりも絞ったって言った方がいいかもしれないですね。小売りって基本的には標準化して、ドミナント出店して物流や人の効率を高めていくものです。で、オペレーションやマネージメントをシンプルにして同じ形のものを展開するのがチェーンストア理論と言われているものですが、居抜き出店って店舗サイズがバラバラで、標準化できないんです。
出店するエリアも、成長しようとすると飛び地に出さざるを得なくなるんですよね。 なので、売り上げ1000億ぐらいの時に既に九州から関東まで店舗群を持っていた。普通の小売業でいうと、異常な状態だったわけですね。ところが新築で出店するとなると建築費がかかる以上、投資効率が最も高いものに絞らなきゃ駄目で、そこでモデル転換をすることになった。データマーケティングよろしく、一番効率的なのは売り場面積1200坪(当時)とわかって、1つの商圏が大体5㎞ぐらいで8割商圏だったので、ちょっと重ねて8㎞ぐらいの店舗間距離を空けておくのが一番効率的だった。そこに集中して出していくっていう標準のモデルに戻していったんです。
高橋:その分析自体は亀田さん自らされたんですか。
亀田:銀行でも調査部にいましたし、データ分析は得意だったんです。それこそ僕がトライアルに入った1番の理由でもあるんですけど、データがあったんですよね。今でもよくトライアルはデータマーケティングをやってる会社って言われるんですけど、昔からデータを大切にする会社だった。
高橋:それはどこからきているんですか?
亀田:創業オーナーがITの人間なので、むしろデータから価値が生まれるが故に小売業始めたぐらいの感じなんですね。小売業が先に大きくなっちゃったんですが、元々はITで、データの価値が分かっている会社。
高橋:オペレーションとデータっていうのは、どういう関係にあるんでしょうか。
亀田:データがなければ、飛び地だとか、様々な店舗サイズがある時に経営できなかったと思います。データがあったから様々なサイズやエリアがあっても共通化できるものとそうじゃないものの整理ができて、経営ができた。だから不可分ではないんですよね。
高橋:なるほど。 ちなみに1200坪っていうのは、大体どんな感じのお店と思えばいいんですか?
亀田: スーパーセンターという業態で、生活必需店が揃う店舗です。嗜好性の強いものバラつきの激しいものはあんまりないですけど、普段の生活を楽しむ、あるいは生活をしなきゃならない上で必要なものを全て用意している。だから食だけではなくてヘルスアンドビューティー、最小限のアパレル、ホームセンターが置いてるような軽家具ぐらいまでは用意してます。
高橋:ターゲットみたいなのもあるんですか。 年齢層とか男女とか。
亀田:ターゲットというか、最終的にうちは地方で絶対必要な店舗を目指してます。必需店なんですよ。
「失敗していいよ」
亀田:うちが 1番大切にしてるのはお客さんにとってちゃんと役に立つか、きちっと使われるかどうかっていうことですが、ちょっとレジカートの話をしていいですか。タブレットがついているカートなんですけど、最初は皆から反対されたんです。タブレットはそれなりの価格するからまともに投資しても合わないだろうってことで、スタートは、お客さんの携帯電話をアタッチしてやってくれるといいなと思ったわけですよ(笑)。
高橋:デバイス代がかからないと(笑)。
亀田:そうは言ってもいきなりお客さんの携帯を出させるわけいかないんで、最初は携帯のサイズでタブレットをセットしたわけですよ。でも誰も使わない。やっぱりあんな小さい画面じゃ見てくれないことがわかったので、大きいタブレットにしました。で、多少見られるようになったので、レコメンド、お客さんが店内回遊する時にナビするぞと思うわけですよ。で、購買データからレコメンドに力を入れるわけですけど、これも誰も使わない。
高橋:そうなんですね。
亀田:使われなかったですね。じゃあどこで使われるようになったかっていうと、決済だったわけですよ。お客さんの店舗の中での1番の課題はレジ待ちのストレスですよね。これを解消してあげる、ここにフォーカスした時にあのカートが劇的に使われ始めた。
高橋:なるほど。それは、どうやって発見されたんですか。
亀田:もうやりながらですよね。もう本当にエフェクチュエーション理論じゃないですけど、何が当たるのか分からないじゃないですか?
高橋:そうですね。
亀田:当初思っていた通りに発展するわけではなくて、使われ方が違ったり形が変わったりしてスケールし始めるわけですよね。なので、うちが大切にしたのはまずはやってみよう、失敗していいよという文化です。ただ正義を軸にっていうのがあって。
高橋:正義を軸に?
亀田:言い換えると大義ですよね。本当に社会の為になることであればまずやってみようと。日本の企業は失敗を許さない傾向があるように思いますが、どこかの真似をするんじゃなくて新しいイノベーションを構築しようと思ったら失敗するのは当たり前です。あのカートもそういう紆余曲折があった。
一般的なテック企業の場合は現場と離れているから中々上手くいかないことが多いと思いますが、うちは現場があるので、実際に使っているお客さんを見ながら検証や改善ができる。それで決済機能が重要なことがわかったんですが、計算機能、つまりカートに入っている商品の合計金額が見られていることもわかってきた。 提供側としては、ついクーポン出したりしたくなるんですが、その結果、合計金額を小さくするとお客さんからは不評になるんです。そんな風にお客さんと対話しながらものを作っていく。これが、リアルの現場とテクノロジーを分かっている企業の強みだとずっと思っています。
高橋:決済機能だ、というとこに辿り着くまでどれぐらいかかったんですか?
亀田: 2年ぐらいじゃないですかね。
高橋:費用対効果は合うんですか。
亀田:そろそろ合い始めます。 要はレジ本体やそこに配置する人件費とのトレードオフなんですよね。投資を振り替えて、キャッシュフローが残るという話になってきます。
高橋:そうですか。買い物しているお客さんは、5000円いっちゃったからもう買うのやめようみたいなことって起こらないんですか。
亀田:それが逆で、予算内に抑えようとするってことは予算額まで買えちゃうわけですよ。いまの合計金額がわかればまだあといくら買えるなという心理状態になるみたいです。
高橋:なるほど、まだあと200円あるなみたいな。その200円に対して「これが買えます」ってレコメンドが来るんですか。
亀田:そこまではやってないですけどね(笑)。
#2 来店頻度向上の理由 地域に根づき育つ経営
地域に必要なものを強化
高橋:今のカート以外にもエピソードみたいなものはありますか。
亀田:さっきターニングポイントって話があったんですけど、僕は本当にさっき言った金融機関で得た情報を最大限使ってるんですけど、ディスカウントフォーマットって市場のゆがみを利用して成長するんですよね。
高橋:市場のゆがみを?
亀田:市場で溢れた商品、賞味期限間近の商品とかを安くまとめ買いをして売るのがスタートなんです。そうするとお酒や菓子みたいな嗜好品が大多数で、定番品を強化していかなきゃならない。最終的にお客さんに定期的に来てもらうために1番課題だったのが、生鮮とヘルス&ビューティーの強化でした。地域に絶対必要なものはスーパーマーケットとドラッグストアなんです。
おかげさまで生鮮は劇的に良くなってきて、総菜も伸び始めていて、投資家さんからも評価していただいてます。それはお客さんの来店頻度が上がっているからです。そこをちゃんと1つずつカテゴリーを育てていく。
流通網の強みを活かして生鮮も強化
亀田:生鮮の話でいうと、地場スーパーさんはローカル性が強くて市場との関係が大切だったりするわけですよ。うちが新しく出店したって地場の小売業スーパーさんとはしっかり関係ができている。簡単には崩せないので、生鮮がなかなか強くならなかった。
ただ最近は食文化が変わってきて生産も変わってきてますよね。肉が1番早く工業化しましたけど、貝類とか甲殻類とか大体輸入じゃないですか? そうすると今度は商社との関係にスケールメリットが働き始めるので、そういうところに入っていったんです。
高橋:なるほど。
亀田:地場の近海魚の焼き物や煮物は簡単には勝てないんですけど、寿司や刺身、あとはバナナとか輸入商材は多少勝てるようになって、そういう変遷をたどって少しずつ生鮮が強くなってきた。店舗のバックヤードの機械化に力を入れてきたんで、サプライチェーンも川上も変わってきたことで、やっとお客さんにトライアルグループの生鮮も総菜も美味しくなったよねって言ってもらえるようになりました。10年ぐらいかかったんじゃないかな。
高橋:ちゃんとしたお弁当もこんなに安くて大丈夫かなって思っちゃうぐらいですが、でも食べたら凄くおいしくて、あれはそういう10年のご苦労の結果ってことなんですね。
#3 データに基づく顧客起点のまちづくり
人口激減社会の産業構造とは
高橋:以前お話を伺った時に産業構造を本気で変えたいというお話がありました。
亀田:変えたいっていうか、変わらなきゃならないと思っているんですね。DXってよく言われていますが、僕は明治維新の頃と今が似ていると思っています。石炭石油エネルギーが動力源を持って、いろんなものが大量生産され、大量消費し始めたのが明治維新後です。それから産業革命が起きるわけですが、当時は概念だけの話だったけど、今はデータに基づいてできるようになってきています。
要は顧客起点で産業構造を再編成していくタイミングだと思っているんです。人口構造もそうですよね。江戸時代は3000万人しかいなかったのが急激に増えて1億2000万人になった。で、今は人口が減り始めているって言われても、1990年ぐらいからの変化って1億2000万人がちょっと増えてちょっと減っただけですから、特に実感がないと思います。
高橋:言うほど変わっていないんですよね。
亀田:これから劇的に減るわけですよね。特に団塊世代の人達が後期高齢者なわけで、生まれてくる子供達って70万人しかいないわけですよね。もう劇的に人数違っていて。70万人が80年生きたとしても5000~ 6000万人ぐらいにしかならないわけですよ。この変化がこれから起きる。
もう1つは急激な円安。以前のように強い円を使って海外から安く仕入れることができないし、海外の人件費が高騰していて、インフレにならざるを得ない。消費する人も少なくなるし、もっと早く減るのは働く人です。だから働く人の生産性をどれだけ上げるかが重要課題です。特に建築業界が顕著で、就職する人はバブル期の3分の1まで減っているんです。
高橋:そうなんですか。
亀田:だから建築料は劇的に高騰しています。物流と建築は流通のインフラで、ここが劇的に変わるのは分かってるんで、ここに経営資源を投下して物流会社の物流提携、九州物流研究会みたいなものを立ち上げていってるんですね。DXの中で顧客起点に街づくりをしなきゃならない、生産性を上げていかなきゃならないって話ですよね。
あとは環境問題ですね。うちはものを売る会社ではありますが、無駄なものは作らない、無駄なものは消費しない、その中で生活をどれだけ豊かにできるかっていう方向に発想を変えなきゃならない。そうすると店舗の在り方って変わらなきゃならないですよね。
うちが出店してるところってローカルだから、人口が減っていくとサービス提供する場所も高齢化していって、後継者がいなくなる。今、宮若という地域で実験をやろうとしてるんですけど、小中学校の空き物件を活用させていただいてるんです。
いろんなインフラがどんどんなくなっていって、上下水道が維持できるんだっけっていう話も出ている。これから劇的な構造変化が起こる中で、それぞれの企業が役割を考えてやらなきゃならないと思っています。
あるべき競争戦略
亀田:実際にやっているのはリテールAI研究会もそうだし、流通業界にうちもジョインして一緒にやりましょうっていう話をさせてもらってますし、九州物流研究会も同じでイオン九州の柴田社長とは色々話をさせてもらって一緒にやり始めてますけど、共有できるものを共有していく。
今まで日本は、意味のない差別化戦略を取り過ぎていると思うんですよね。標準化できるものは標準化して共同利用した方が社会全体の効率が上がります。マイケル・ポーターがスケールメリットをちゃんと追いましょう、その中でどう差別化するかってことを言ってるのに、物流会社もばらばらで生産性がどんどん下がってる。配送なんて共同利用した方がいいに決まってるじゃないですか。
落選してしまったんですが、九州大学箱崎キャンパス跡地のまちづくりというプロジェクトがあるんです。スマートシティっていろんなところでいろんな実験されているんですけど、どこも顧客不在なんですよね。DXって顧客のデータが手に入る環境ができてきてるから出てきた発想のはずなのに、顧客不在のスマートシティの実験が始まっている。小売業の1番の価値は、顧客とリアルの接点を持ってることですから。
高橋:週何回もいらっしゃいますもんね。
亀田:そうなんですよ。継続的に顧客と関係を築けるから顧客を分かった上でいろんなサービスを一緒にやりたかった。それは箱崎や宮若に限った話じゃなくて、産業構造を変えて本当に効率的な社会を一緒に作っていきましょうと。
実際にNTTさんとデジタルツインの発表をさせてもらいましたし、NECさんと一緒になって、Face IDを使って顧客を理解できる環境を用意する話をしていますし、そういういろんな企業と連携して新しいチャレンジをしていきたいと思っています。
高橋:全ての住民の生活必需品を提供するっていうのがトライアルさんの提供価値っていう話でいくと、日本の構造の中の1番のボリュームゾーンのところでずっと商売されてきている。だから顧客理解についても1番ターゲットゾーンのお客さんをご存知ってことですよね。ニッチなお客さんよく知っていますっていう会社さんはたくさんいらっしゃると思うんですけど、1番カバー範囲が広いかもしれないですね。
亀田:おっしゃる通りですね。都心は人口が多いから細分化、専門化しやすいですよね。ローカルは経営共創基盤の冨山さんなんかが言ってる話で、コングロマリット化すべきなんだと。1社がある程度まとめてサービス提供すべきなんだと。全くアグリーで、いろんな企業が都心に向かう中で、うちはローカルでちゃんと生活をサポートできる。なので、今おっしゃっていただいた通りで全住民をターゲットにしているので、いろんな幅広いデータは拾えているかもしれないですよね。
ここは逆に言うと使命感なんですけど、これから本当にローカルを維持するため決して簡単なことはではないと思っているので、いろんなサービスを集約して提供できるような企業になっていきたいなと思っているんですけれどね。
高橋:地方の人口の減り方っていうのは本当に激しいですし、地方ほどインフラも老朽化しやすいでしょうし、高齢化も進んでて、確かにコングロマリットなのか分からないですけど、しっかりした企業がちゃんと地方の生活を支えるっていう状態を作らないと中々難しいですよね。
亀田:そういう意味では行政サービスなんかも元々コンビニさんがやっていますけど、ひょっとしたらうちも今は全然やれてないですけど、やるべきかもしれないし、いろんなコミュニティの場所としてリアル店舗の価値ってこれからまだまだ出てくると思っています。