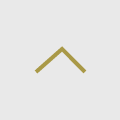#1 トライアルHD社長ターニングポイント 肩書だけの経営者だった
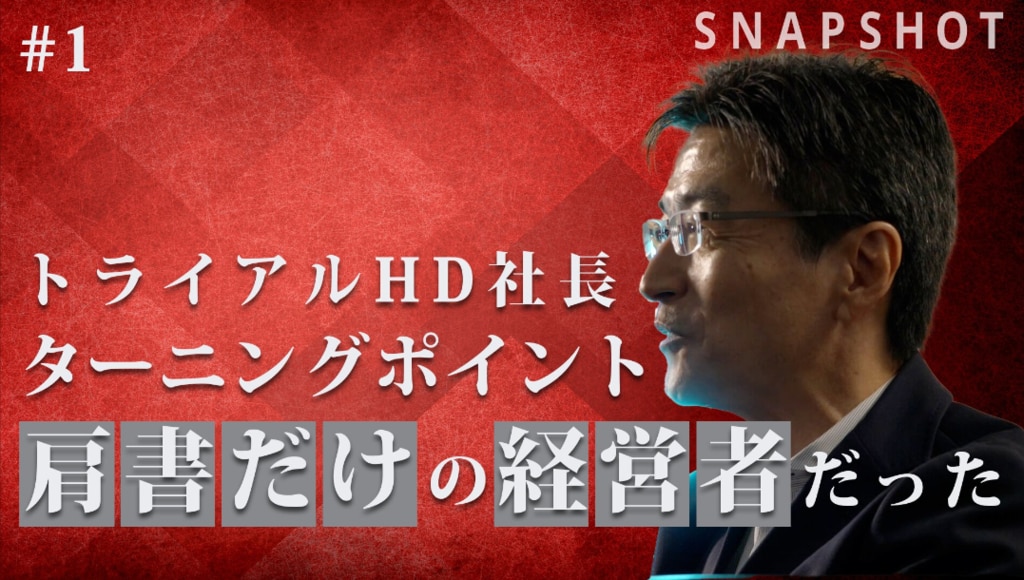
代表取締役社長
亀田 晃一 氏
第二話では亀田氏の人物像に迫る。キャリアのスタートは富士銀行(現みずほ銀行)で、自ら希望する銀行業務を次々に経験。そしてM&A推進を担当したのが出会いとなり、トライアルカンパニーに入社した。豊富な金融業界での経験はトライアルの経営にどのように活きているのか。また、トライアルホールディングス代表取締役社長としての今後の展望について話を伺った。
銀行で鉄壁の経験をしただけでは経営者になりきれなかった
高橋:トライアルに入社されるまでのご経歴を教えていただけますか。
亀田:僕はバブルの真っ最中に旧富士銀行に入ってですね、大学も経営学部だったんですけど、経営にはめちゃくちゃ興味があって、わがままだったんです。実は2カ店目、3年目で辞表を出してるんですよね。
高橋:今だと3年で辞める人多いですけど当時だとすごいですね。
亀田:当時も結構、富士銀行大量退職時代っていうのがあって、なんとなく先輩が辞めてるし、辞表出していいんじゃないかという雰囲気があって(笑)。辞表出した理由は、僕は自我の強い人間で、銀行に入る時から調査部に行かせてくれと言ってたんですよ。
高橋:今は全然そういう面影がないですけどね。
亀田:そうですか(笑)。だいぶ柔らかくなってるかもしれないですね。調査部に行かせてくれるというのを信じて入社して、2カ店目でいけるもんだと思ってたのに行けなくて辞表を出したら、引き止めてくれて調査部に配属されました。そこからわがままを貫き通すようになりましたね。
高橋:言ったら通るものだと。
亀田:そうそう。そこからずっとやりたいことを言い続けてきて。調査部には3年半ぐらいいました。その後は長い案件をやりたくてプロジェクト推進室というところで臨海副都心の都市開発だとか、つくばエクスプレス、当時は常磐新線鉄道って言ってたんですけど、USJの誘致だとかを担当していたんですよね。その中でキャッシュフローをどう長期の時間軸で考えるかっていうのを勉強させてもらいました。
そのあとはベンチャーキャピタル、企業再生をやる部署を経て、最後M&Aをする部署に行きました。その時に、トライアルが北海道のカウボーイっていう上場企業を買収しようという話があって、銀行の中からじゃなくて、トライアルに入ってM&Aを推進したんです。
僕の個人的なターニングポイントが実はこれで、銀行で偉そうなこと言ってもやっぱりサラリーマンだったなってつくづく感じたのは、交渉がある程度まとまりそうだとなれば、もうM&Aの担当者としては、よしと思うわけじゃないですか。で、当時は社長だったんですけど、オーナーの永田に報告した時に「お前これやるべきだと思うか」って言われたんですよ。取締役なんだから聞かれて当然なんですが、「それ決めるのあなたじゃないの」と思ってしまったんです。情けないですよね。
高橋:なるほど。
亀田:銀行はM&A成約させれば終わりだから、その感覚でトライアルに入って、自分は肩書だけは取締役になっていたのに、全然経営者じゃなかったなと。今でも鮮明に覚えています。
高橋:コンサル業界だとよく、分析をして「雨が降りそうです」じゃなくて、「傘を持っていけ」「いや持っていかなくていい」っていうところまで踏み込んで提案しろと言われます。でも経営者はそう言われて本当に傘を持っていくかいかないかを決めるんですよね。いくら条件がよくても買うか買わないか、お前はどう思ってるんだ、これはなかなか鮮烈な質問ですね。
亀田:財務内容も当時まだ盤石じゃなかったんで、まとめればいいわけじゃないと本当に思ったんですね。結局やることを決めたんですが、具体的な投資が始まったタイミングでリーマンショックが起きたわけですよ。いやそれはないでしょって言いたくなりました。銀行からの資金調達が大変になって、逆に言えばそこを契機に飛躍できたと思うんですけど、 そういう転機がありましたよね。
#2 ビジネスは用意してスタートしない トライアルHDの本当のイノベーション
0→1の世界ではROIが無意味
高橋:銀行時代にいわゆるファイナンスと呼ばれるものは全部ご経験された。支店での下積み時代があって長期のプロジェクトファイナンス、そのあとはベンチャーキャピタルで起業、そのあとが企業再生で最後がM&A。もう鉄壁ですね。
亀田:トライアルにきて本当によかったなと思うのは、全ての知識を活かせるっていう形で、これだけ色んなことをやる会社は多分ないですよね。
高橋:トライアルさんの中では、どの時期の銀行時代のご経験が生きたっていう感じになるんですか?
亀田:さっき言ったようにM&Aの延長線上で入ってるわけですけど、本当に資金繰りが大変な時にどういうファイナンスをするかっていうのはひとつあります。あと、僕はROI信者なんですが、デジタルの世界で本当のイノベーション起こすにはROI考えちゃいけないんだなっていうのは、逆にトライアルに入って学んだ話です。
高橋:失敗していいとか、2年間待つとか、ROI的には何言っちゃってるのってことですよね。
亀田:その通りです。最近非常に好きな本で、サラスバシーさんの「エフェクチュエーション理論」っていうやつと、モハン・スブラマニアムの「デジタル競争戦略」があるんですが、やっぱり失敗前提なんですよね。新規事業を立ち上げるっていうのは、ROIで測れないなっていうのは頭では理解できていたんですけど、肌感覚としては、ベンチャーキャピタルですら、金融系・銀行系のベンチャーキャピタルだったが故もあるかもしれないですけど、キャッシュフローが見える中での判断だったんですよね。
0→1の世界って当たり前なんですけどROIなんて考えてないですよね。まずはお金ないわけですよ。お金ない中でどうやって事業立ち上げるかじゃないですか。だから今度は「許容可能な損失」っていうエフェクチュエーション理論では、「手中の鳥」、今手元にある中でスタートさせようねと。無料でやれぐらいの勢いなわけですよ。
で、今度は「クレイジーキルト」っていう3つ目の原則があって、パッチワーク、色んな人の協力を買ってキルトを作る話なんですね。でその次の「レモネード」、使えなくなったものをいかに使うか。さっき言ったカートもわかりやすいと思うんですけど、色んな失敗して、辞めたは簡単なんですけど、何がうまくいってなかったのか、どう転用するのかを考え続けるっていうのが大切なんです。
最後「機中のパイロット」、要はそのときの状況で判断しなさいと。大きな目標は変えるべきじゃないけど、ちっちゃな目標はゴールが変わると書いてあって、確かに新規事業ってそうです。最初ハワイに行こうとしてたけど、南の島に行ければいいわけで、フィジーでもいい。ハワイまでは嵐があって行けないからフィジーに行こうよって話。
そういう経験ができたのは逆に言うとトライアルに入ってからで、銀行で培ったものもたくさん使えるけど、トライアルで学んだことってやっぱり本当に多かったですよね。
顧客起点で産業構造を再編する必要がある
高橋:なるほど。 2つ目の本「デジタル競争戦略」はどんなものですか。
亀田:これはさっき言ってた話なんですよ。デジタルって、インターネット革命でありデータで繋がっていくことじゃないですか。繋げていく時には、物を起点としたプロダクションエコシステムっていう、今まで日本の産業構造の中でずっといわれてきたのに実はできてない部分をやりにいかなきゃならないっていう話。
もう1つ、産業構造が変わるっていうのもまさしくこのデジタル競争戦略に基づく話なんですけど、顧客を起点にもう1回産業構造を再編しに行く必要があると。
車の例が紹介されてるんですけど、車に乗るなら駐車場やガソリン、保険がまず必要で、行き先でも駐車場を確保したり、道順は把握しなきゃならない。ガソリンスタンドや休憩するスターバックスの情報もいります。これが車、ドライバー起点でのエコシステムですね。これをデータとして繋ぎ込む必要がある。
つまりクローズドの世界でデータをいくら整理しても役に立たなくて、またぐと劇的な変化を起こせる。そういう環境の変化がこれからどんどん起きてくるっていう話が書かれてる本です。
高橋:なるほど。それが九州物流界とかにも繋がっていくわけですね。
#3 人と人・人と物を繋げる場所を作る
リアルの場と人をつないでローカルの生活必需店に
高橋:最後になりますけど、そのような様々なご経験を踏まえて今後どういうキャリアを実現されていきたいでしょうか。
亀田:トライアルでやりたいことは本当にたくさんあって、1つはさっき言ったようにローカルの生活をどうやって維持するかは本当に社会課題だと思っていて、うちはそこに基盤を設けている以上、ちゃんと色んなサービスを繋げる場所が必要なんですよね。 店舗っていうのは、今まではモノと人を繋ぐ場だったかもしれないですけど、これからは人と人も繋げられるかもしれないし、店舗を不動産として捉えると、そこで食事をすることもできるかもしれない。そういう広がりを実験的に宮若でやり始めてて、研修施設、大小の店舗、オフィス、ホテル、ゴルフ場まで用意してるんですよね。
ローカルで豊かな生活を送るために、生活必需店、インフラとしてやれることがもっともっとあるんじゃないかと。オンラインだけの世界ってもうかなり行き着きつつあって、これからリアルの場所と人、モノと人、人と人を繋げるチャレンジをしていきたいなと思っています。
九州は食もいいし、観光資源もたくさんあるし、TSMCが出てくれて産業インフラもこれから多分かなり良くなってくるので、グローバルに色んなことをできると思ってます。だから福岡をシリコンバレーにしたいんだみたいなことをちょっと大々的に言ってしまいましたけど、本心から思っている話で、地方都市の産業構造って都心よりもコンパクトで変わりやすいだろうから、うちである程度やろうとしてるみたいな話で。
高橋:そうですよね。 1億2000万人、都市とローカルっていうのをどこで線引きするかっていうのはあるかもしれないですけど、もしかすると半分ぐらいはローカルに住んでるかもしれないですよね。かつローカルは都心よりも当然人口密度も低くて点在してるんで社会課題としてはめちゃくちゃ大きいんですよね。
それぞれの地方都市の周辺にそういう場所が点在してる状況だと思うんで、そう考えると、何かひとつモデルを作れればそれはものすごく横展開しやすそうですよね。
亀田:そうなんですよ。日本は課題先進国だと言われてるじゃないですか。ローカルは更に課題先進国なんですよね。そこでちゃんと作り込めると国内でもそうかもしれないし、もっと言うとグローバルに展開できるんじゃないかなと思ってます。
高橋:なるほど。社会的意義があって、それこそ正義・大義が求められるチャレンジであるということですね。本日は長時間ありがとうございました。
亀田:ありがとうございました。