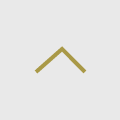#1 業績赤字での社長就任

代表取締役社長
楠元 健一郎 氏
高橋:まず社長に就任された時の会社の状況について教えていただけますでしょうか?
楠元:はい。私が就任したのは2021年4月で、コロナ禍の中でどうやって会社を生き残らせるかというところでした。コロナが始まる前から営業利益が若干下がってきて、2019年度は赤字だったんですね。なので、会社存続というよりは確実な再生をしなきゃいけないという局面だったと自分では思っていますけどね。
高橋:ご就任される前から厳しい状況だったってことですね。そのような中で、再生施策についてはどのような考えを持たれていたんですか?
楠元:元々、前職が銀行員で、再生事業に関わっていた目線で見ると、コロナはまさに未曾有の事態でした。ですので、「もともと赤字になった原因」と、「コロナが明けた時に世の中がどうなっているか」をセットで考える必要がありました。
私自身、再生の経験は長い方ですが、今回のようにコロナのような特殊要因が加わるケースは初めてでした。業績悪化の原因も含めてすべてが一度コロナによって根本から崩されたわけです。だからこそ、新しい形に作り替えることで再生できるんじゃないかという、ある意味ポジティブに捉えることができた部分もありますね。
高橋:なるほど。確かにコロナ前の状況での業績が悪い原因を特定したところで、また状況が変わっているっていう話ですね。一方でコロナ後って誰も見たことのない世界なわけですが、そこはどう想像、予想されたんですか?
楠元:ひとつには「コロナ後のあるべき姿」について、リモートにはなりましたが、従業員の皆さんと忌憚なく議論できたことがあります。コロナという特殊な状況だったからこそ、率直な対話ができて、「みんなでこんな未来を目指そう」というビジョンができたので、もうその未来を作ることに専念した方がいいと感じたわけです。
もちろん、収益モデルの作り替えは大事です。ただそれ以上に、自分たちが例えば「焼き鳥屋」として、コロナ後の世界でも前向きに頑張っていける何か、そうした“人を中心にした”メンタルの部分も含めた施策を、経営のど真ん中に据えた方が良いと考えました。
そこに皆の気持ちが集約できれば、あとはビジネスモデルの話は自然とついてくる。ですから、再生計画においては、ある意味、人心掌握のようなところが一番の肝だったと思います。
高橋:現場の方と議論していく中で思い出に残っているシーンはございますか?
楠元:まだコロナの中でどうなるか先行きが分からなかったにも関わらず、「未来計画」という3カ年計画を作ってお見せしたことがあったんですね。まだ行動制限がある中で、もちろんマスク付けて換気なんかもしてはいましたが、全国で13回、リアルでタウンミーティングをやったんです。
ご家族に反対された方もいたんじゃないかと思いますがみんな来てくれて96%ぐらいの出席率だったんです。ポストイットに想いを書いて貼ってもらうんですけど、ものすごい数でした。不安だらけの中で声を聞いてくれる状況があることが、一つの光明だったんだろうと解釈しています。終わる時にほっとした顔、笑顔になっていたのが、すごく印象に残っていますね。
#2 ビジネスモデルを3つに分解「業態・収益・人材」
高橋:再生計画自体は社長就任前から作り始めていたんですか。
楠元:そうですね。就任前から「事業再生ADR」を申し立てる準備を進めていたんです。当時はCFOでしたので、まずADRを成立させ、そのうえで社長に就任し、策定した再生計画を自ら推進していくという流れになりました。当時は緊急事態宣言、まん延防止措置、アルコールの提供制限、営業時間制限なんかが重なって7割ぐらい売り上げが飛んでいて本当に苦しかったです。
高橋:居酒屋は損益分岐点が低い業態じゃないですからね。7割売り上げが飛べばどうしようもない状況ですね。
楠元:我々のポートフォリオの約75%は居酒屋業態で、コスト面でもコロナ前からすでに厳しさが見えていました。ですので、例えば「赤字店舗をすべて閉店して縮小均衡型の再生を図ろう」と考えても、実際はそう簡単ではないんです。仕入れと原価のバランスの問題もあって、我々のような業界では、大きな環境変化の中で“縮小均衡”という考え方は成り立たないんですね。
あと、僕はよくビジネスモデルって3つに分けて話すんですよ。業態、収益、人材モデルって。たとえば、立派な業態モデルや収益モデルを作っても、今の人材でやり切れますか?とか出てくることがありますね。何かが置き去りになってしまうのとうまくいかない。この3つのバランスをしっかり誰かがコントロールしないとおかしくなるというのが僕の中で一つのセオリーです。今回の再建については、何を新しいモデルとしてコントロールしていくのかというロジックを作り上げることと、それをどうやって浸透させるかがすごく大事で、しかもそれを短時間でやっていかなきゃいけないといった時に、まさにChain Consultingのサービスも含めてありがたかったですよね。
高橋:ありがとうございます。
#3 人口減少時代でも人のサービスに価値を求め続けたい
高橋:ポートフォリオの組み替えみたいなお話はあったんですか。
楠元:再生プロセスの中では、もちろん整理しながら進めてきました。ただ、まずは各業態が独立して事業として成り立つ形を作ること、すべての業態を平等に同じレベル感で捉え、皆が気持ちを集約できるものを作る必要があったんです。
私はそれを「本質会議」と呼んでいましたが、その本質の部分をみんなで共有し、それをベースに「今やるべきこと」を整理してもらう。この順番が大切だと考えていました。
高橋:なるほど。ポートフォリオの前に、個別の事業がそもそも成り立つようにというのが大前提だからということですね。やっぱりトップ自ら、子会社の方に降りていかないと難しかったという状況なんですか。
楠元:そうですね。元々僕も外からきている人間で、特に悪い状態から入っていますから、真実を知りたかったんですよね。なので、全部見て回って、これから良くなっていくことを前提に体制を組み替えていきたかった。
高橋:銀行ご出身でそこまで現場を大切にしてるのが珍しいというか、だからうまくいったのかもしれないなと思うんですけど、やっぱり人材に対する思い入れがすごくあるということなんですか。
楠元:そうですね。人口減少の時代に向かって、今後どういうビジネスモデルになっていくのか他人事みたいな言い方で僕も興味あるんですけど(笑)。だけど最後の最後までやっぱり人のサービスで価値を求め続けたいなと思いますね。最後までフェイストゥフェイスの営業をしつつ、その他の作業体系の中で効率化をしていきたいので、やっぱり人を大事にするのが最優先ですよね。
高橋:我々もサービステックというネーミングで、人の手によるサービスにいかに付加価値をつけていくか、そのバックアップをどうするかっていうことを考えてます。
楠元:よろしくお願いします(笑)。そういう話が大好きなので。
高橋:最後の質問です。そういう改革を経て、昨年度5年ぶりの黒字化を達成されました。今後の方向感を教えてください。
楠元:正直まだ道半ばだと思っています。ただ、社員が前向きに盛り上がってくれているので、次のステップとして、より具体的な未来を示そうとしています。この計画では、社員一人ひとりがよりリアルに将来像を描けるような取り組みを進めています。
たとえば、既存の業態の中で、3年後の具体的なイメージもすでに示しています。それが見えたことで、「これができるなら何でもできるよね」「海外にも出ていけるよね」「国内のマーケットが縮小していくように思えたけど、僕らはむしろ拡大できるよね」といった声が次々に出てきているところです。
高橋: 2021年に作った未来計画はそれなりの達成状況だったってことなんですか。
楠元:達成とは言いにくいですが、社内的にどん底を見た社員から見ると、今なりにやり切ったよねという数字は上がっていると思うんです。その背景になっている、人事施策や教育施策、一個一個の業態の何を磨き上げるかに対して、どういう投資をしたとかについては、ほぼ100点満点だと思っています。全部やりきったと思っております。給料やボーナスやいろんな処遇など、どんどん人の投資には回してたので、それなりにやる気になってくれてるんじゃないかなと思います。
高橋:社内目標は100%やり切ったので、社員の方々がついてきて、じゃあ次の3年という雰囲気になって盛り上がっているということですね。よくわかりました。ありがとうございました。