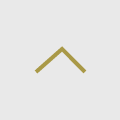#1 50歳でやきとり屋のオーナーになるという夢が叶った
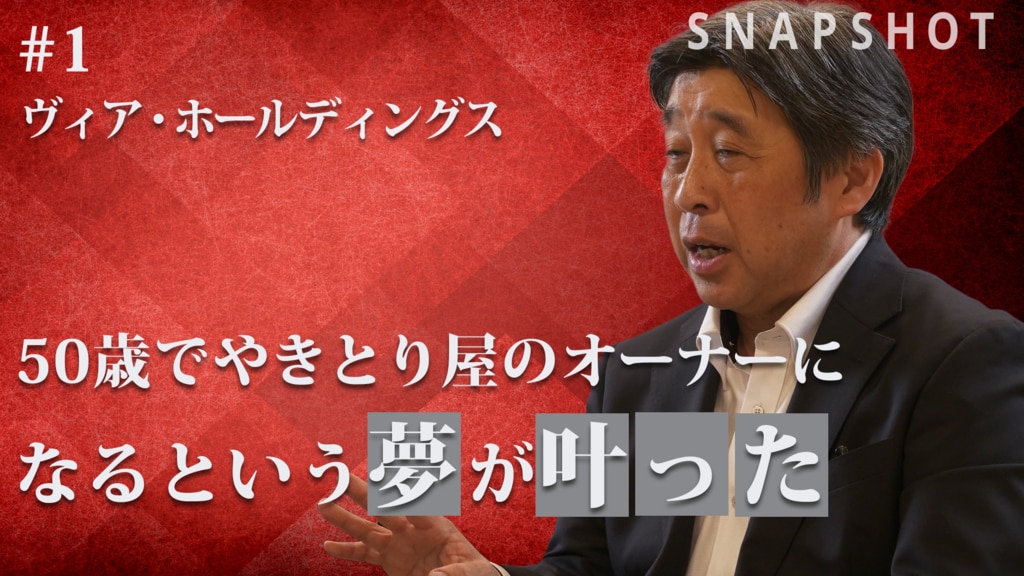
代表取締役社長
楠元 健一郎 氏
第二話では楠元氏の人物像に迫る。ヴィア・ホールディングスへの入社前、楠元氏は銀行員として複数企業の事業再生、M&A等に携わってきた。その経験が現在のヴィア・ホールディングスの経営にどのように活かされているのか。現場とのコミュニケーションを大切にする楠元社長にお話を伺った。
高橋:キャリア編ということで、銀行でのご経験についてまず教えていただけますか。
楠元:銀行に30年おりました。いわゆる事業再生に関わるような部署の在籍期間が21年延べであったんですね。審査部だとか、ソリューションを提供するような部署のトップもやらせてもらいました。ただ、他の銀行員の方々と違うとすると、メインバンクとして取引先の事業再建のお手伝いをさせていただくことが多くて、出向で半年間行きっぱなしとか、ハンズオン型で内部に入って、デスクやパソコンも一緒に置かせてもらうような働き方を10社くらい経験してきました。
高橋:10社の中で特に記憶に残っているとか、キャリアの転換点になったような案件はございますか。
楠元:あります。時代背景としてはバブル崩壊後の再生の時代で、建設会社や不動産会社が多かったんですが、外食企業とわりと似ているんですよ。200も300も現場があって、正社員が現場のリーダーで、あとは大工の方だったり、いろんな方が働いていて、そういうところが面白かったですね。工事現場に見学に行くと、飯場があって、ちょっとこれから一緒に飲みに行こうよって技術者の方々と一緒に飲ませていただいたり、そういう経験は良かったですよね。
高橋:なるほど。そういうところが現場の意見を吸い上げなきゃという考えにつながっているんですね。
楠元:そうですね。工事原価をコントロールしてるのは会議室じゃなくて現場だと。何かのドラマみたいなんですけど(笑)、本当にそういう感じですよね。
高橋:なるほど。その後、外食に転身されたわけですけど、なぜ外食だったのかと。
楠元:実は当社(ヴィア・ホールディングス)は、14年前に一回担当させていただいているんです。あと、元々は印刷会社だったのを再建・再生するのにすかいらーくの創業家の横川4兄弟が資本支援をしたところから始まっているので、たまたま私は20年前にすかいらーくを担当していたので、そんなこともあってこの会社に関わることが多かったんです。
高橋:なるほど。いろいろな接点が。
楠元:僕は大学の時にずっと焼き鳥屋でアルバイトをしていたんです。銀行員で50歳までお金を貯めて自分の焼き鳥屋をやろうと思っていて。今から思うと50歳になってからお店を持とうなんて現役の店長には申し訳ないですね。ただ結果的に、私どもの会社は焼き鳥の業態で全体の70%の店舗数を持っているので、そういった意味では個人的な夢がかなったのかもしれないですね。店長とオーナーでは似て非なるものですけど商売という意味では。
高橋:焼き鳥屋でのアルバイト経験に加えて、すかいらーくさんとかヴィアさんを銀行員としてご担当されて、出向先では建築や不動産関係の建て直しもされ、そこからの外食の経営者としてご転身、そういうキャリアですね。
楠元:そうですね。だから結構共通項が多かったかなと思いますね。
高橋:いざ店長を束ねる経営者としてトップに就かれた時、コロナでしたが、その時の心境はどんな感じだったんですか?
楠元:どうだったかな。現場からは「今度の社長は銀行から来てるし、会社を良くしてくれるでしょう」っていう、お手並み拝見の目で見られるから、平時だったらどうやって現場の気持ちを僕の方に向けさせようかなと余計なことを考えたかもしれないですね。
でも、実際には業績不振でさらにコロナだったから、とにかく早く現場を知って前に進めなきゃいけないという心境だったし、受け入れる側も不安があってそこはすんなり進んだかもしれない。早くみんなと一緒にマスクしながらだけど車座になって、コロナ後の未来について語り合いたいなっていう心境だったっていうことですかね。
高橋:それが建築現場にも行かれていた経験の上にあったんでしょうね。それがないとなかなか現場に行くのって怖かったりします。
楠元:銀行員って現場の皆さんから見たら、ひ弱そうに見えるじゃないですか。どういう目で見られてるのかなってありますからね。ちょっと怖かったです。
高橋:私もお寿司屋さんの企業変革をお手伝いしていた時、厨房に入ってお寿司を握らせてもらったことがあるんですけど、そもそもネタが冷たいんですよね。心の準備なく触って「冷たっ」って言おうもうんなら大笑いですよ(笑)。現場行くのはやっぱり大変だなと思いましたよね。それが社長だとなおさら、「それもできないのか」みたいな。
楠元:そうです。現場で鉄筋の部品につまずくと大笑いされますからね。「転んでるよ」みたいな。その雰囲気の中で耐えられるかなという怖さはありますよね。
高橋:新人を笑っているのと同じ感覚ですよね。
楠元:同じ釜の飯を食うなんて言いますけど、そういうことって結構重たいよなって思っています。銀行って債権者、債務者の立場なので、そこから来るいくつかの勘違いってやっぱり生まれちゃうんですよ。本部の方は「銀行さん、銀行さん」って言ってくれますけど現場は関係ないですからね。「邪魔だよ」だけなので(笑)。
高橋:私も現場へ行くと役に立たないやつ来たみたいな扱いですからね(笑)。
楠元:「できたら邪魔しないでくれる」という目で見られますからね。だから経験があったことは、少なくともこの会社でみんなと未来を語る上においてはすごく良かったです。
#2 社長と現場の距離が近すぎるデメリット
高橋:一方で、社長と現場の距離が近すぎると、それはそれでデメリットがあるっていうお話もあるんですよね?
楠元:どういう経営のスタイルを目指すかによって違うかもしれないんですけど、少なくとも私の場合は外様で緊急事態でもあり、短期間でコロナの中で立て直さなければいけなかったので、全部の事業会社に入りこんで現場とファーストタッチしていったことの効果はすごく大きかったことは間違いないんです。
でもガバナンスとしては現場のリーダーをちゃんとつけていくのがやっぱりいいんだろうなと思った時に、今は私と現場の距離が近すぎるので、間に入る人たちの立場がなくなったり、ダブルスタンダードが生じるんですね。権限をどうやって移行させていくかを考えながら、正しい距離を定義づけなきゃいけないなは思っています。
高橋:なるほど。次の社長、子会社の社長、次の部長は育ちづらいというデメリットがあるということですね。
楠元:そうですね。順当に考えれば、次の本当のトップがその中から生まれてくるわけですから。なので、今のうちにそのポストを目指して自分たちも頑張ろうとなっていくような好循環を作らなきゃいけないですかね。
高橋:社長の仕事って確かに今の事業をちゃんと収益化するっていうのもありますけど、次世代の経営者育成とか、次世代の幹部育成というのもありますもんね。
楠元:なので、現場の話を聞いてくれるいい社長だなって、今ちょっとでも思っていただけているとしても、あの人はいい人だったなで終わってしまうリスクだけは回避しなきゃいけないということです。
#3 歩いているだけで現場を元気にするおじいさんを目指したい
高橋:最後に、今後の目標はございますか。
楠元:そうですね。あまり考えないようにしていたんですけど、今あえて答えるとすると、理想は一線をどこかで引きたいなと思っています。その後皆さんが許してくれるんであれば、ドラマの水戸黄門のように何年もかけて全部のお店を回りながら、御老公様が来てくれたってみんなのモチベーションが上がるような人になりたいですね。
高橋:なるほど。水戸黄門のような。
楠元:ビジネスモデル的な話とか、経験を活かしてコンサルをやって広く伝えていきたいとかじゃなくて、この顔が歩いているだけで周囲の元気が出るようなおじいさんになりたいですかね。
高橋:現場で働いている方のモチベーターというか、現場をエナジャイズしたいということですね。最初から最後まで現場感あふれるお話をありがとうございました。
楠元:ありがとうございました。